ベンダー選定とは?ベンダー選定基準と選定プロセスやポイントを解説
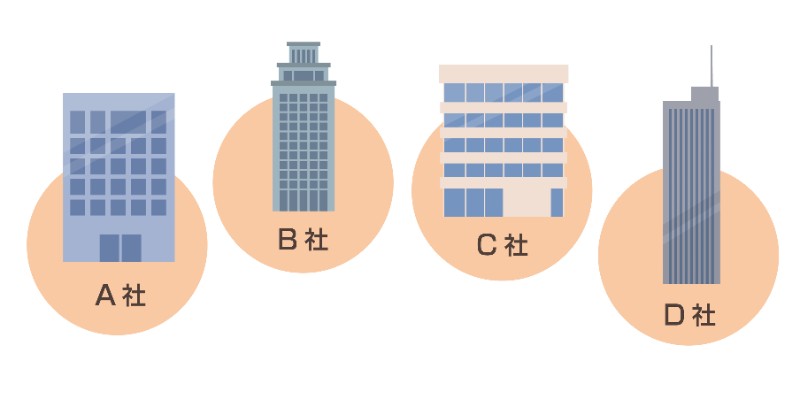
目次[非表示]
- 1.ベンダー選定とは
- 2.ベンダー選定基準を設ける必要性とは
- 3.ベンダー選定のプロセス
- 3.1.ベンダー候補をピックアップする
- 3.2.RFIを作成する
- 3.3.RFPを作成する
- 3.4.選定基準を作成する
- 3.5.ベンダー候補から提案を受ける
- 3.6.評価と選定を行う
- 4.ベンダー選定基準のポイント
- 4.1.安定性や成長性
- 4.2.能力と過去実績
- 4.3.初期費用とランニングコスト
- 4.4.納期と妥当性
- 4.5.要件の網羅性と実現度
- 4.6.開発体制と具体性
- 4.7.保守体制と具体性
- 4.8.SLAや既存システムとの親和性
- 5.ベンダー選定のプロセスを理解して最適なベンダー選定しよう
IT業界においてクラウド事業者やSIer、インフラ業者などの製造元や販売元のことで、システム関連の業者のことをベンダーと言います。
DX推進は企業の経営や業績にも直結する重要な要素ですが、そのパートナーとも言える存在がベンダーです。
自社に合った最適なベンダーを選定することがDX推進の一歩であるため、ただの業者選びと適当に選定するのではなく、二人三脚のビジネスパートナーを選定する心構えでベンダーの選定を行いましょう。
ベンダー選定とは
デジタルツールやサービスの導入やDX推進をするために欠かせない重要な要素がベンダー選定です。
DX推進に向けてハードウェアやソリューションの購入やシステムの開発が必要になりますが、このIT製品やサービスを販売している業者のことをベンダーと呼びます。
様々な企業がサービスや製品を提供していますが、その中から自社に合った最適なベンダーを選定する必要があります。
ベンダー選定は、DX化やプロジェクト成功の要と言っても良いくらい重要なフェーズなのでポイントをしっかり抑えて正しいベンダー選定をすることが求められます。
ベンダー選定基準を設ける必要性とは
ベンダーを選定する前に、まずはベンダー選定基準を設ける必要があります。
数多のベンダーの中から最適なベンダーを選択することは非常に難しく、印象や直感で選択してしまうと、プロジェクト失敗へつながってしまう可能性があります。
しかし、選定するための基準を明確にしていないと、該当するベンダーを本当に選択して良いのかどうかの判断をすることができません。
ベンダーは自社ができることを提案してくるのでどのベンダーも「実現可能で、価格はいくらです」という営業的な内容がほとんどなので、どこを選んでも実現できるのなら安いところを選ぼうという発想になってしまうかもしれません。
価格だけで判断することはリスクがありますし、失敗を防止するためにもベンダー選定基準を設けてしっかりと横ならびで評価する必要があります。
適切なベンダー選定基準に沿ってピックアップしたベンダー候補の中から最適なベンダーを選定することが重要になるのです。
ベンダー選定のプロセス
ベンダーを選定するためのプロセスを解説します。
正しい手順を踏んで、効率よく適切なベンダー選定を行いましょう。
ベンダー候補をピックアップする
まずは、自社のやりたいことが実現できそうなベンダーを10社程度ピックアップしてリスト化します。
ある程度は印象や直感で構いませんが、事業内容や従業員数や過去実績など、コーポレートサイトから判断できる情報である程度の絞り込みは必要です。
大手企業は信頼性が高いですが、費用も高くなりがちなので、中小企業やベンチャー企業も含めて候補に入れてみると良いかもしれません。
RFIを作成する
ベンダー候補をリスト化した後はRFIを作成して、各ベンダーに送付します。
RFIとは、Request For Informationの略で、情報提供依頼書のことを指します。
各ベンダー候補のベンダーの企業情報や技術情報、サービスやソリューションの情報が必要ですが、インターネットのリサーチのみでは情報の粒度がバラバラだと比較検討が困難なのでほしい情報をRFIとしてフォーマット化してベンダーから情報提供してもらいます。
RFPを作成する
次に、RFPを作成します。
RFPとは、Request For Proposalの略で、提案依頼書のことを指します。
具体的にシステム導入の目的や現状、要望などを整理してまとめたものです。
ベンダー側はRFPをベースにして提案内容を検討することになります。
選定基準を作成する
ベンダー候補はRFPを元に提案書を作成しますが、提案を受ける前に各ベンダーを比較検討するための選定基準をあらかじめ用意しておきます。
提案書の提出やプレゼンを受けた際に選定基準に沿って適切な評価をしましょう。
ベンダー候補から提案を受ける
RFP送付後は、ベンダー候補からRFPに対する提案を受けます。
不明確な部分を残したまま契約しないようにこの時点で質疑を通して明確化することを心がけましょう。
評価と選定を行う
提案を受け、RFPの内容を満たしているか、事前に準備したベンダー選定基準に照らし合わせて最終評価をします。
機能や価格だけではなく、ベンダーの組織や体制、担当者などもしっかり確認して依頼するベンダーを決定しましょう。
ベンダー選定基準のポイント
ベンダー選定で重要な要素はベンダー選定基準を設けることです。
どのような評価視点でベンダー選定基準を設けるべきかのポイントを確認していきましょう。
安定性や成長性
ベンダーが企業として安定した経営をしていなければ、倒産や事業縮小のリスクがあります。
また、事業内容や実績から成長性が見えなくても同様です。
万が一、事業縮小や倒産されてしまうと、プロジェクトが頓挫してしまったり、稼働後の保守が無くなってしまう可能性があります。
ベンダーの会社規模や事業、近年の財務状況などを踏まえて、安定性や成長性など企業の信頼性を評価することはとても大切です。
能力と過去実績
ベンダーが得意とする分野や技術と自社の要望がマッチしているかを確認しましょう。
また、過去にどれくらいの実績があるのかを把握すると信頼性が増します。
コーポレートサイトに掲載されていないことも多いので、RFIに記載しておくと良いでしょう。
初期費用とランニングコスト
コストはベンダーを選定する上でもっとも気になる要素のひとつだと思いますが、あくまでもひとつの判断材料としてください。
もちろん予算は重要な要素ですが、コストだけ見てほかを見ないと痛い目を見る可能性もあります。
初期費用やランニングコストが自社の予算感と合っているか、見積もりは根拠があって妥当であるかを吟味しましょう。
納期と妥当性
稼働予定日は自社の要件を満たしているか、妥当なスケジュールであるかを確認しましょう。
あまりにも遅い納期設定の場合は技術要素に不安が見られたり、逆に早く設定されていても現実味がなければ品質低下を招く恐れがあります。
要件にあった現実的で妥当な納期設定を見極めることが大切です。
要件の網羅性と実現度
RFPに記載した要件や課題、機能などを理解し、抜け漏れのない提案になっているかを細かく確認しましょう。
また、実現方法や実現可能性なども確認し、相手方の「出来ます」だけを鵜呑みにしないようにすることで失敗を防ぐことができます。
開発体制と具体性
ベンダーの開発体制も重要です。
ユーザー側から見れば軽視しがちなポイントですが、自社の重要なDX推進をまかせるパートナーです。
企業自体の評価はもちろんですが、きちんとした体制が組まれていて担当者ともうまく一緒に伴走できることも大切です。
また、開発現場は多重下請け構造が蔓延しています。
大手企業に依頼したものの、実際には聞いたこともない会社に丸投げしているということもざらにあります。
社内体制や協力会社を含めた開発体制はしっかりと確認しましょう。
保守体制と具体性
確認したいのはサービスやソリューションの導入時だけの体制や内容だけではありません。
稼働後の保守体制と具体性を確認することも大事なポイントです。
費用や稼働時間、サポート内容、コミュニケーション方法、期間など、どのように保守を考えているのか具体的な内容を確認しましょう。
SLAや既存システムとの親和性
SLAとは、Service Level Agreementの略で「サービス品質保証」を意味します。
保証するサービス内容や責任範囲を定めたものです。
たとえばクラウドサービスにおいて「SLA 99%」と記載があれば「稼働率99%を保証します。」という意味になります。
注意するべき点は、「稼働率99%」は決して高くないということです。
稼働率99%は1か月あたりで7時間程、1年で87時間程の時間サービスが停止することになります。
クラウドサービスを検討している場合は、SLAにも注目しておきたいところです。
また、既存システムからの移行や既存システムとの連携についての確認が必要です。
今まで自動連係していた別の既存システムが、一部のシステムが新しくなることによって、手入力しなくてはいけなくなったので手間が増えるという可能性もあります。
ベンダー選定の段階でどの程度親和性があるのか、どこまで許容できるかなどをしっかりと検討しておくことが重要です。
ベンダー選定のプロセスを理解して最適なベンダー選定しよう
DX推進やデジタルツール、クラウドサービスの導入において、ベンダー選定はとても重要です。
また、ベンダー選定基準を設けることでベンダー候補を適切に評価し、最適な選定を行うことができます。
RFIやRFPをしっかりと記載し、重要なポイントを押さえた選定基準を準備して、ベンダー選定失敗による損失を抑えましょう。









