脆弱性とは?わかりやすく脆弱性の例と危険性・対策を解説
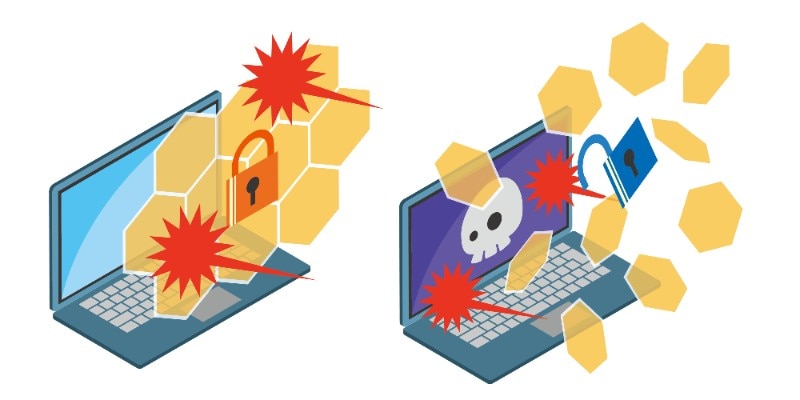
目次[非表示]
- 1.脆弱性とは
- 2.脆弱性の例
- 2.1.技術的な脆弱性
- 2.2.システム環境の脆弱性
- 2.3.人や組織の脆弱性
- 3.脆弱性を放置する危険性
- 4.脆弱性に対して有効な対策
- 4.1.OSやソフトウェアのアップデートやパッチ適用
- 4.2.適切なアクセス制御や監視
- 4.3.社員へのセキュリティ教育
- 5.脆弱性の危険性を理解して適切な対策をとろう
脆弱性はシステムの弱点や欠陥のことで、放置すると外部からの攻撃や内部不正などさまざまな被害に発展してしまう可能性があるものです。
企業では、脆弱性をなくす取り組みや脆弱性を突いた攻撃を防ぐために、適切なセキュリティ対策を行うことが大切です。
脆弱性とは何か、脆弱性の例や脆弱性を放置することの危険性、対策方法をわかりやすく解説します。
脆弱性とは
脆弱性とは、コンピュータシステムやソフトウェアに存在する弱点や欠陥のことです。
脆弱性があると、悪意のある攻撃者からシステム・データの乗っ取りや、不正な操作などの攻撃を受ける可能性があります。
脆弱性は、情報漏えいやシステム停止など、企業にとって重大な損害を引き起こす可能性があるため、未然に対策を講じることが重要です。
しかし、システムの脆弱性は様々な原因で発生するため、完全に排除するのは難しいものです。
- ソフトウェアがアップデートされて、新たな脆弱性が発見される
- 攻撃者がセキュリティ対策を回避する新たな攻撃手法を生み出し、新たな脆弱性が発見される
- システムの運用や管理における人為的なミスや不注意により脆弱性が生じる
- 新たな技術やシステム環境が導入されることで、未知の脆弱性が発生する
このように、脆弱性は一度対策すればなくなるというものではなく、常に新たな脆弱性が生まれるものと考えて、継続的な対策が求められます。
脆弱性の例
脆弱性は、大きく下記の3種類に分けられます。
- 技術的な脆弱性
- システム環境の脆弱性
- 人や組織の脆弱性
それぞれ具体的な脆弱性の例を見てみましょう。
技術的な脆弱性
技術的な脆弱性とは、ソフトウェアやハードウェアなどの技術的な不具合や欠陥によって生まれる脆弱性です。
サイバー攻撃などの脅威からシステムやネットワークを保護できない状態になります。
技術的な脆弱性の主な例として、以下のようなものが挙げられます。
- SQLインジェクション:ウェブアプリケーションに対して、不正なSQL文を投入することで、データベースから機密情報を抜き出せてしまう
- バッファオーバーフロー:プログラムに対して、特定のデータを入力することで、プログラムの機能を悪用して、攻撃者がコンピュータにアクセスできてしまう
- クロスサイトスクリプティング(XSS):ウェブアプリケーションに対して、不正なスクリプトを埋め込むことで、ユーザーの情報を盗めてしまう
これらはほんの一例で、ほかにも技術的な脆弱性は様々なものがあり、システムやネットワークを保護するためには、常に対策が必要です。
システム環境の脆弱性
環境の脆弱性は、システムやアプリケーションが運用される環境に起因する脆弱性のことです。
環境の脆弱性の主な例として、以下のようなものが挙げられます。
- 不適切なネットワーク設定:ファイアウォールやルーターなどのネットワーク設備が適切に設定されていないと、不正アクセスやDoS攻撃などが発生する可能性がある
- 不適切な権限設定:アカウントやプログラムに不要な権限を与えると、攻撃者が利用して不正アクセスを行う可能性がある
- アップデートやパッチの適用不足:新しいバージョンやセキュリティパッチがリリースされるたびに漏れなく適用しないと、既知の脆弱性が残ってしまう可能性がある
システムの設定や運用に不備があると、その不備を突いた攻撃者の侵入を招いてしまうため、適切な対処が必要です。
人や組織の脆弱性
人や組織の脆弱性は、人の行動や組織の体制、プロセスなどに起因する脆弱性のことです。
技術的な脆弱性とは異なり、攻撃者は高い技術や知識を必要としません。
人や組織の脆弱性の主な例として、以下のようなものが挙げられます。
- 人的な脆弱性:社員の不注意や不正な行動よる情報漏えいの可能性
- 業務プロセスの脆弱性:重要な情報を扱う際のプロセスに不備があったり、形骸化していることによる、内部不正の可能性
- 企業文化の脆弱性:社員のセキュリティ意識の低さや、セキュリティ対策の甘さによるセキュリティ事故発生の可能性
人や組織の脆弱性に対しては、企業全体でのセキュリティ意識の向上が必要です。
脆弱性を放置する危険性
脆弱性を放置すると、攻撃者がそれを利用して様々な被害を引き起こす可能性があります。
脆弱性を放置する危険性として考えられる具体例を見ていきましょう。
不正アクセスによる情報流出などの被害
攻撃者は企業の脆弱性を突いて、ハッキングやスパイウェアなどの技術を駆使して、ネットワークやシステムに不正にアクセスを試みます。
不正アクセスを許してしまった場合の主な被害は次のとおりです。
- 個人情報や機密情報が盗まれる
- システムの正常な稼働を妨害される
- 悪意のある広告が表示される
不正アクセスにより、業務が滞ることで企業に経済的な損失が生じます。
また、個人情報流出などの被害が出れば、顧客や取引先からの信頼も失われることになるでしょう。
マルウェア感染による情報漏えいやシステム破壊
企業の脆弱性を突いたマルウェア攻撃は、攻撃者が企業のネットワークやシステムに存在する脆弱性を利用して、マルウェアを意図的に感染させることで行われます。
主なマルウェア攻撃は以下のとおりです。
- ランサムウェア:データを暗号化し、復号のための身代金を要求する
- サプライチェーン攻撃:セキュリティ対策の弱い関連企業や取引先をマルウェア感染させ、目的の企業に侵入する
- IoTマルウェア:セキュリティ対策が不十分なIoT機器をマルウェア感染させ、企業のネットワークに侵入する
脆弱性を突いたマルウェア攻撃によって、企業は、機密情報の漏えいや身代金の要求、運用停止など重大な被害を被る可能性があります。
また、長期的に企業の信頼やブランドイメージに悪影響を与える場合もあるでしょう。
内部者による不正や不注意による被害
脆弱性を突いた攻撃は悪意のある外部者によるものだけではありません。
社員や関係者などの内部者が悪意を持って不正を働いたり、不注意やミスで被害を出したりする場合もあります。
内部者による被害の例は以下のとおりです。
- 機密情報の不正持ち出し:情報持ち出しのチェックの甘さを突いて、不正に情報を持ち出し流出させる
- 不正なアカウントによる情報窃取:削除されていない退職者のアカウントを悪用して、情報を盗み業者に売る
- 社外に誤って顧客情報を送付:顧客情報を含むファイルにパスワードをかけ忘れて社外宛てに顧客情報を送ってしまう
社内のセキュリティ対策状況をよく知る内部者は、不正を働く動機があれば外部者よりも容易に攻撃ができてしまいます。
実際、大きなニュースとなった情報流出事件には、セキュリティの甘さを突いた内部者による犯行も少なくありません。
脆弱性に対して有効な対策
脆弱性を突いた攻撃の被害を防ぐための対策はどのようなものがあるのでしょうか。
脆弱性に対して有効な対策を見ていきましょう。
OSやソフトウェアのアップデートやパッチ適用
OSやソフトウェアのアップデートやパッチ適用は、もっとも重要な脆弱性対策の一つです。
アップデートやパッチは、開発者が発見された脆弱性を修正し、セキュリティーの強化を図るためにリリースされます。
アップデートやパッチを適用することで、脆弱性を修正し、ハッキングや不正アクセスなどの攻撃から保護することが可能です。
アップデートやパッチの適用はできるだけ早めに実施しましょう。
脆弱性を突いた攻撃は、脆弱性の公開後すぐに行われることが多く、対処が遅れるとそれだけ危険にさらされる期間が長くなってしまいます。
被害を防ぐためには、アップデートやパッチの適用を定期的に行うことが重要です。
適切なアクセス制御や監視
適切なアクセス制限や監視も、脆弱性対策として有効な手段です。
アクセス制限は、不正アクセスや不正な操作を防止するために、アクセス権限を必要最低限のユーザーにのみ付与することです。
例えば、機密情報にアクセスできる権限を持つユーザーを限定することで、機密情報の漏えいを防止できます。
監視は、システムやネットワークに対する異常なアクセスや操作を検知し、早期に対応できるようにすることです。
アクセス制限や監視によって、外部からの不正アクセスや、内部からの不正操作を検知し、早期に対応することが可能となります。
また、監視ログは、万が一被害にあった際に、原因や攻撃者を特定するのにも役立ちます。
社員へのセキュリティ教育
人や組織の脆弱性を解消するには、社員へのセキュリティ教育が重要です。
セキュリティ教育は、社員が正しいセキュリティ対策を実施できるようにするのが目的です。
例えば、フィッシングメールや標的型メールなどの脅威に対して、正しい対応方法を知らせることで、社員が警戒することができます。
また、社員がセキュリティ教育で組織のセキュリティポリシーを理解することで、組織的なセキュリティ対策の強化を図ることが可能です。
セキュリティ教育は、定期的・継続的に実施し、社員が正しいセキュリティ対策を実践できるようにすることが重要です。
脆弱性の危険性を理解して適切な対策をとろう
脆弱性にはさまざまな種類があり、次々と生まれるため、常に対策を怠らないことが大切です。
脆弱性を足がかりに社内ネットワークに侵入された際に重要情報が盗まれないよう、オンラインストレージに重要情報を退避しておくのも有効な対策といえるでしょう。
セキュアSAMBAはセキュリティに定評があるビジネス向けの国産オンラインストレージサービスです。
オンラインストレージの利用を考えているのであれば、無料から始められるセキュアSAMBAをぜひご検討ください。









