IT化とICT化の違いはなに?IT化とICT化の違いを理解しよう
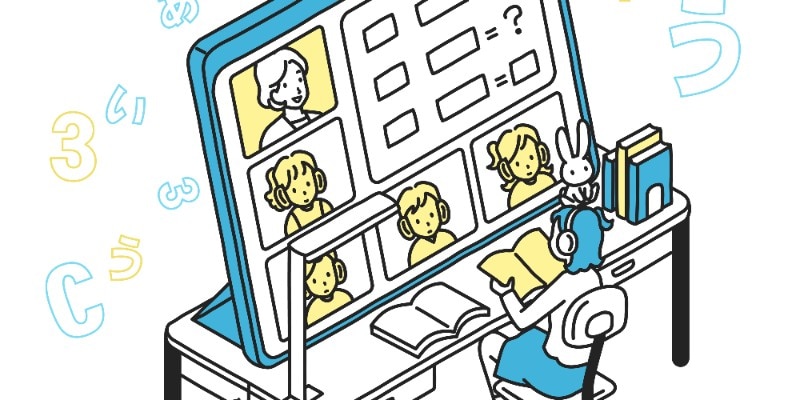
目次[非表示]
- 1.IT化とICT化の違いはあまりないが使い分けされている
- 2.IT化からICT化へ移行され始めている
- 3.ICT化で実現できることやメリット
- 3.1.情報共有しやすくなる
- 3.2.距離の制限を受けないタスク参加
- 3.3.工数・時間の削減になる
- 3.4.新しいアイデアが生まれやすくなる
- 3.5.働き方の多様性につながる
- 4.ICT化に必要なこととは?
- 4.1.導入コストの確保
- 4.2.使いこなすための教育制度を設置
- 4.3.使えない人のためのサポート体制の整備
- 4.4.セキュリティリスクから守る環境を整備
- 5.ICT化の具体的活用法
- 5.1.医療介護のICT化:人を救う
- 5.2.教育のICT化:学習機会を増やす
- 5.3.農業のICT化:身体的精神的負担を減らす
- 5.4.交通のICT化:地方活性化につながる
- 6.IT化とICT化の違いを理解して適切に進めよう
IT化とICT化の違いを正しく理解できているでしょうか。
ICT化はIT化の延長にあり、単なる作業効率を向上させるための手段ではありません。
ICT化に必要な知識や具体的な活用方法を知り、実践に活かしましょう。
IT化とICT化の違いはあまりないが使い分けされている
IT化とICT化は同じような意味合いで使われることがあります。
しかし、厳密に言えばIT化とICT化の目的は異なり、使い分けがされています。
IT化の目的はデジタル機器の普及促進や機能を向上させることで、IT技術そのものを指しています。
一方、ICT化の目的はデジタル機器を使ったサービスの開発や、その延長にある活用方法を指しています。
このように、IT化とICT化は違いというより用途に応じた使い分けがあるのです。
IT化からICT化へ移行され始めている
国際的にはICTをITと同義で使うことが一般的で、日本でもそれにならい、これまで「IT」と呼ばれていたものが「ICT」へ変更されるようになりました。
総務省の情報通信政策では、すでにITではなくICTとして認知されています。
日本は国際的にもICT化が遅れている状態です。
IT化が広がってきた中で、次の段階であるICT化の強化に焦点をシフトさせる必要があるでしょう。
ICT化で実現できることやメリット
ICT化に取り組むとどのようなことが実現できるようになり、メリットを得られるようになるのかを確認していきましょう。
情報共有しやすくなる
ICT化の最大のメリットは情報共有しやすくなることです。
ICT化の例として、クラウド上に保存したファイルやコミュニケーションツールを利用した会議などがあり、場所を問わず必要な情報をリアルタイムで閲覧できるようになります。
ICTを活用したサービスやツールを利用することは業務効率化には必須です。
距離の制限を受けないタスク参加
各個人がIT端末とコミュニケーションツールを持っていれば、離れた場所にいても同時に共同タスクに参加できるようになります。
企業であれば本社と現場がパソコンを介してコミュニケーションがとれるようになるため、現場が海外であっても同時にオンライン会議へ参加できます。
また、学校や塾では、生徒一人一人にタブレット端末を貸与することで、自宅にいながらオンライン授業を受けることがICTの活用で可能になります。
工数・時間の削減になる
ICT化を進めるにあたり、小さなことから無駄を削減していくようになります。
代表的なのはペーパーレス化です。
印刷して、署名して、捺印して、次の部署に回して、FAXして、といったアナログな業務フローを短縮できると、工数や時間を大幅に削減できます。
新しいアイデアが生まれやすくなる
無意味な工数を削減できると、時間や思考力にも余裕が生まれます。
その結果、より生産性の高い仕事に注力できるようになり、サービスの質を向上させたり、新しい商品開発に取り組むためのリソースを確保がしやすくなるでしょう。
働き方の多様性につながる
ICT化が進み、遠隔コミュニケーションやペーパーレス化が当たり前になると、無駄な会議や残業が減り、オフィス環境が改善します。
その結果、社員が自由に働き方を選べる企業が増えています。
これまでは転居や子育て、介護などでスキルを持っていても活かせないままキャリアが閉ざされてしまうことがありました。
働き方が多様化すると、企業は優秀な人材を手放さずに済むようになり、働き手も企業も選択肢が増えていくでしょう。
ICT化に必要なこととは?
ICT化をスムーズに進めて、ICT化を実現しやすくするためには、ただIT機器を配布すればいいわけではありません。
IT機器だけではなく、ICT化に必要なものはどのようなことかを理解しておくことが大切です。
導入コストの確保
ICT化を浸透させるには、導入するためのコスト面を考慮する必要があります。
このコストとは、デジタル機器の購入や配布費用のほか、ツール、セキュリティソフトにかける費用、ひいては人材育成のための時間や経費を割かなければいけません。
あらかじめ、導入コストをいかに確保し投資していくかを決めておきましょう。
使いこなすための教育制度を設置
サービスやデジタル機器を使うための知識や操作方法などを、しっかり相手に伝えられるシステムが重要です。
例えばオンライン授業を始めるにあたり、子どもたちに1台ずつのパソコンやタブレットなどを貸与したとします。
サービスを正しく安全に利用するためには、デジタル機器の使い方を理解して活用できるようになるための教育制度が必要と言えるでしょう。
使えない人のためのサポート体制の整備
一人ではサービスを使いたくても使えない人のためのサポート体制も必要です。
ITリテラシーを高めようとしても、高齢者やハンディキャップのある人によっては、どうしても制限が出てしまうこともあります。
介助者の協力やサポート人員の配置が求められる場合の対策も考えましょう。
セキュリティリスクから守る環境を整備
ICT化が進むにつれ、セキュリティ対策の重要性が増していきます。
情報の共有が進むと、無関係の第三者までその情報に触れることができてしまうのがICT化の弱点です。
意図しない接触はもちろん、悪意ある攻撃から情報を守るための環境を整える必要があります。
ICT化の具体的活用法
生活のインフラが、ICT化によって高い利便性を発揮し始めているケースが増えています。
ICT化が活用されている例を紹介します。
医療介護のICT化:人を救う
超高齢化社会を支える新しいサービスとして、医療や介護分野でのICT化が急がれています。
福井県と石川県では県境をまたいだ広域クラウド型救急医療連携システムが設置され、救急搬送中の患者情報をクラウド上で連携することで、救命率のアップに成功しています。
教育のICT化:学習機会を増やす
教育機関におけるICT化は、パンデミック下で世界的にも加速しました。
自宅から出ずにオンライン授業へ参加でき、双方向でコミュケーションが取れるため、新しい学習の在り方として認知されつつあります。
また、文部科学省も教育現場へのICT化に力を入れており、「教員のICT活用指導力の基準」に基づいた教員研修プログラムも組まれています。
農業のICT化:身体的精神的負担を減らす
慢性的な人不足と定期的な巡回、繊細な温度管理が必要な農家にとって、ICT化は心身ともに負担を減らす一手になっています。
沖縄の農家では温度変化や設備の故障等を、クラウドサーバーを介し、電話やSMSで通知してくれるシステムを導入しました。
時間と手間を省けた分、浮いた時間を活用し、さらなる品質向上を目指せるようになったのです。
交通のICT化:地方活性化につながる
これまでアナログな経路検索しかできなかった地方の公共交通機関でも、ICT化によって簡単に検索できるようになりました。
その結果、国内外の観光客が地域バスを利用しやすくなり、地方活性化につながっています。
岐阜県では規模の小さいバス路線のバス情報フォーマットを整備し、アプリやリアルタイム運行状況を知らせるシステムを開発しています。
さらに外国人観光客が多いというデータに基づき、多言語検索も可能にしたため、利用者のターゲット層を大きく広げることに成功しています。
IT化とICT化の違いを理解して適切に進めよう
IT化とICT化は違いがあるというものではなく、基本的には同じ概念の上に存在しています。
ICT化はIT化の延長にあり、人とモノがつながり、新しい価値を創造するためには欠かせなくなっています。
しかし、セキュリティ対策が不十分なまま情報の共有化が進むと、無関係の第三者がアクセスし、情報を流出させてしまう恐れがあります。
ICT化において最も注意するべき点がセキュリティリスクの放置です。
クラウド上でファイルを保管するのであれば、強力なセキュリティ環境を維持できるオンラインストレージが必須となります。
「セキュアSAMBA」は、細かくアクセス権限を設定した運用ができるオンラインストレージです。
閲覧できるユーザーや端末を厳密に絞れるため、同じ社内でも無関係の社員のアクセス制限がおこなえるので利便性だけでなくセキュリティ面でも安全です。
無料でも使えるオンラインストレージ「セキュアSAMBA」で、安心してICT化を進めてはいかがでしょうか。









